2011年6月24日(金)〜7月30日(土)に武蔵野美術大学美術館で開催された「ムサビのデザイン コレクションと教育でたどるデザイン史」展。本展にあわせ、これまで大学にかかわった教員たちが、ムサビのデザインのコレクションと研究・教育について語る対談シリーズが行われました。本シリーズは、コレクションのみならず、ムサビのデザインの研究・教育のあり方を歴史的に伝えるものです。今回はそのなかから、本学名誉教授の島崎信と、工芸工業デザイン学科教授(当時)の小松誠による対談を紹介します。
体得の教え
島崎:武蔵野美術大学の美術館棟のリニューアル開館にあわせて、かつての工芸工業デザインコースの教育について話をしてほしいと依頼がありました。確かに工デの元教員に関して言えば、年齢を重ねているのは私ぐらいしかいないので受けることにしたのですが、では誰と対談をしようかと考えたとき、現在の工デの教員のなかで、私は即座に小松君だと思ったのです。どうしてかというと、私は豊口克平先生の下で60年代半ばから教壇に立っていたのですが、ムサビのデザイン教育を「受けて」はいないのです。だから受けた人から話を聞かないとわからない。小松君はまず武蔵野美術大学の短大に入学し、初めてできた専攻科に進み、そしてその後にスウェーデンのグスタフベリに行ってリンドベリのもとで勉強なさって、帰国後フリーで活動した。その後にムサビで教員になったわけです。そういう意味ではムサビのデザイン教育をいろいろな角度から見られる人ということで、小松君に話を聞くほかないと思ったわけです。
小松:私が高校生の頃は、全世界でスカンジナビアデザインが一世を風靡していました。1950年代のことです。高校では勉強ができず落ちこぼれで、やっぱり美大かなって考え始めた頃に、デザインというものも初めて知りました。そしてこのスカンジナビアデザインにすごく憧れていたのですが、ちょうどムサビには、加藤達美先生や島崎先生、私が入学した頃にはまだいらっしゃらなかったんですけども芳武茂介先生など、北欧に縁のある先生がいらっしゃいました。その頃芳武先生の著書『北欧デザイン紀行』(相模書房)が出されたこともあり、非常に憧れを抱いて入学しました。
島崎:いざ入学してみて、がっかりしませんでしたか?
小松:いえいえ。私にとってはパラダイスのようでした。なぜかというと、とにかく勉強が嫌いでしたから、ムサビに来て「手を動かす」ことが面白くて、面白くて仕方なかったのですね。
島崎:まあムサビでは手を動かすことが重んじられていましたからね。
小松:私は論理的な思考とは対極にあって、とにかく手仕事といいますか、手を動かしてものを作っていくことに憧れていましたから。芳武先生が盛んに「体で覚えていくのだ」みたいな内容をおっしゃっていたのを思い出しますね。体得というような言葉をよく使われていましたよね。とにかく素材をいじりながら考えていくということが面白かったです。しかも、短大の工デは4年制学部と全く同じ先生が教えてくれていました。

島崎:それは他の学科にはない工デの特徴のひとつでしたね。私は64年にまず非常勤として着任しましたが、ある時期は工デのなかのインテリアデザインコースだけでなくクラフトデザインの木工も受け持っていました。
小松:島崎先生が大学に着任された64年に、私は短大の2年を終えて、専攻科に入りました。ちょうど専攻科の第1期生なのですが、その時に授業で島崎先生と初めてお目にかかるわけです。
美術学校と高等工芸
島崎:60年代に工デで教鞭をとられていた先生方のラインナップを見渡すと、菱田安彦先生、加藤達美先生、堤浪夫先生、飯田三美先生、私それから芳武茂介先生が美術学校(現・東京藝術大学)出身なのですよね。
小松:そうですね。
島崎:それとインテリアの豊口克平先生、インダストリアルデザインの佐々木達三先生、廣田長次郎先生の出身校が東京高等工芸(現・千葉大学工学部)です。美術学校と高等工芸とを比較したときに、美術学校では伝統的な手仕事的な感覚を大切にしていましたし、一方の高等工芸では物事を理論的に体系立てて学ぶことに力点が置かれていました。その両校の特徴から影響を受け、工デでは手を動かして物事を考えるという教えが重んじられ、同時に最初の2年間でクラフト、ID(インダストリアルデザイン)、インテリアに横断する基礎的な教育が行われていたのでしょう。こうしたやり方はいまも続いていますか?
小松:はい。現在も入学後の1年半の期間に各コースのうちの4つの講座を選んで体験し、その後に進むべきコースを各自が選ぶようになっています。
島崎:やはり工デでは、幅広く人間の生活や暮らしについて知った上でなければ制作できない、という面があるでしょう。
小松:そうですね。その教えは今も私のなかにも非常に強く残っています。自分の制作にも影響していると思うのです。私は短大に在籍していましたが、在籍当時は芳武先生が主任教授でした。残念ながら豊口先生からは直接教わったことはありません。ただしわれわれの授業の講評には来てくださり、その時に「ものを提示するだけではなく、そのものが置かれる空間を含めたイメージスケッチを書きなさい」と言われたことがすごく印象に残っています。
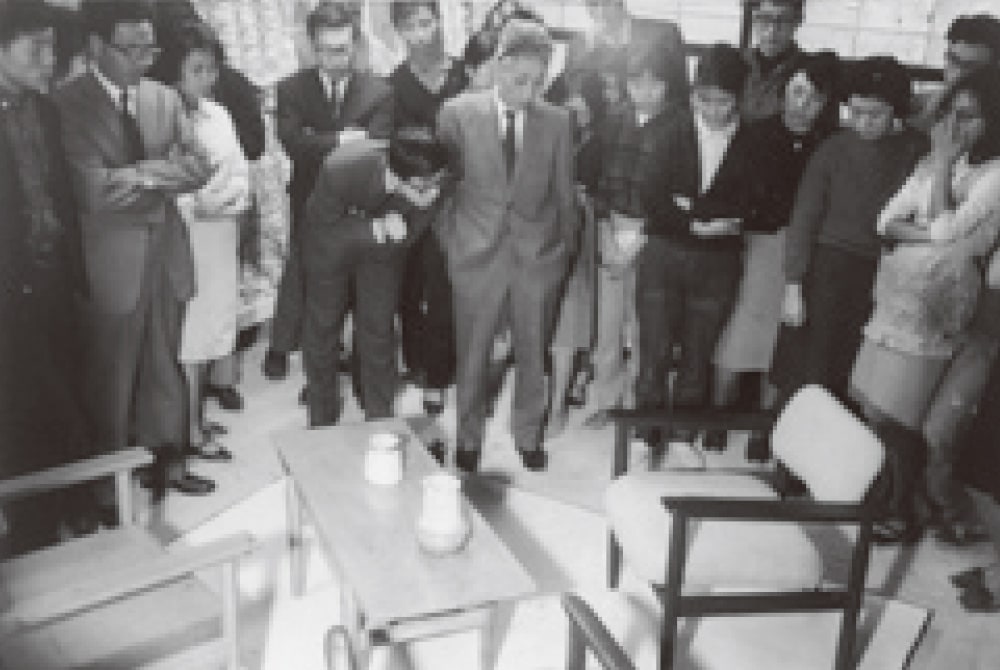
島崎:かつてはたとえコースが違っていても、他のコースの先生が少なくとも講評に出てくださることはよくありました。私が受け持った講義系の授業でも、工デのなかのインテリア以外のコースの学生も対象にした授業をけっこう受け持っていました。
小松:豊口先生と芳武先生は、産業工芸試験所(産工試)出身でいらっしゃいました。産工試といえば、機関誌である『工芸ニュース』という素晴らしい雑誌がありました。私たちが学生の時には、それを皆でこぞって読んだものです。当時まだムサビには教科書がなかったので、それをむさぼるように読み、そのバックナンバーを探すのもひとつの競争でした。
島崎:やはり情報が少なかったこともあるし、少ないだけに情報に対して皆がハングリーでしたね。
小松:今は情報がありすぎて、選ぶのが大変ですね。
島崎:近代以前は「図案する、デザインをする」とは、色や形など何かを付加することでした。それが近代に入ると、いろんなことを削ぎ落していくことこそがデザインだと考えられるようになった。それと同じことで、本当の情報を選ぶために探すのではなくてむしろ無用な情報を削ぎ落としていく、という時代になったのでしょう。インターネットが始まった頃、自分の手元に世界中の情報が自由に入ってきますよと言われたけど、考えてみたら一個人としてそんなに情報はいらない。
小松:情報に対して判断するのではなく、そのまま答えにしてしまう傾向があるのだと思います。もっと自身で削ぎ落としたりしないといけないのでしょうね。
島崎:そういう意味では、手で考えるということはとても重要です。デンマークでは「ものづくり」ということを説明するにあたりこんな教えがあります。「まず頭でものを考え、考えた指令が指先にいき、鉛筆で形を描く。そしてその書いたものを目で見て、見たものが脳に入り、再び考えなおす。この脳と目と手を介してつくられるサーキットこそがクリエイションだ」と。「だからスケッチはできるだけ大きく書きなさい。そして原寸図をいつも書きなさい。そして曲線などは描けるだけ全部鉛筆で描いて、いらないものを消していき最後に一本残る線、それが君の線だ」と言われてジーンときたのを今もよく覚えています。インテリアの授業でも学生にとにかく原寸図を描かせていたのもそのためです。
実物の強さ
小松:私は芳武先生との接点は意外と多くて、芳武先生が日本クラフト協会を設立され、事務所兼ショールームが千駄ヶ谷にあり、そこに友人がアシスタントで電話番として勤めていたのです。そのためによくそこに足を運びました。すると芳武先生がいらっしゃるし、作品もいっぱい置いてありました。そういうのを見ながら、夜は常に宴会になってしまうのですが、芳武先生も時々出てこられましたね。
やはりあのころに受けた影響は大きいようです。実物を間近で見たり、触れたりできたのはすごく勉強になりましたね。
島崎:その「実物の強さ」からどれだけのことを得られるかは、結局のところ学ぶ側の姿勢にかかっているのだけれど、教える側にとってもいろいろなものを集めることは自分自身の勉強になります。
小松:確かにそうですね。ある程度の点数が集まってみないと意味がないですね。そういう意味ではこの美術館の椅子のコレクションは、うらやましい限りです。
島崎:うらやましいとは?
小松:椅子以外のメディアとなると、工デにとって教材になるようなコレクションはあまり収集されていないですから。たとえば焼き物は収集されていますが、古いものでいわゆる名品ばかりです。制作する学生にとってもっと勉強になるような、現代の器などがもう少しコレクションのなかに増えることを願っています。
島崎:かつて工デの他の先生方に教育的な理念でそれぞれのコースに関係する作品や資料を集められたらいかがか、と申し上げたことがあります。けれども皆さん当時はあまり関心がなかったようですね。それからインダストリアルデザインなどは、技術革新が激し過ぎてコレクションには適しません。ついこの前までどこの家にもあったビデオ(VHS)がDVDにとって代わられようとします。そうすると、VHSにとって不可欠なビデオテープの入手ができなくなってしまう。かつてID研究室の佐々木達三先生からは「島崎君、きみは椅子を集めていていいね」と羨ましがられました。その点、陶器類やガラス類のクラフト製品であればずっと集め続けられるわけです。
小松:美術館の椅子のコレクションへの憧れもあって、私が在外研修に行ったときに集めてきたティーポットを研究室の棚に並べています。ああいうものは触らなきゃ意味がないですね。残念ながら美術館では、さわると怒られますが。だから触れる美術館というのがあってほしいですね。「生活用品」と言いながら触ったら怒られるのは、ちょっと矛盾していると感じます。
島崎:椅子のコレクションも予算がないところから始まりました。それでもコツコツと続けているうちにこれだけの規模になったのです。この機会に、収集を美術館へ提案すればいいと思いますよ。
小松:そうですね。名品の焼き物と違い、デザインものの焼き物は決して高価ではないので。大学にとっても美術館にとっても、より一層いいコレクションに成長してもらいたいと思います。
[2011年5月10日、武蔵野美術大学美術館棟にて収録]

武蔵野美術大学名誉教授。1932年東京都生まれ。1956年東京藝術大学卒業、東横百貨店(現・東急百貨店)家具装飾課入社。
1958年JETRO海外デザイン研究員として日本人として初めてデンマーク王立芸術大学に所属、1960年同建築科修了。帰国後、国内外でインテリアやプロダクトのデザイン、東急ハンズ、アイデック等の企画立ち上げに関わる傍ら、武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科で教鞭をとる。また家具や生活用品に関するデザイン展覧会やセミナーを多数企画。北欧やデザイン関連の著作も多数に及ぶ。日本フィンランドデザイン協会理事長、北欧建築デザイン協会理事、鼓童文化財団特別顧問、有限会社島崎信事務所代表、NPO法人東京・生活デザインミュージアム元理事長。

武蔵野美術大学名誉教授。1943年東京都生まれ。1965年武蔵野美術短期大学工芸デザイン学科卒業。1970年より1973年まで、スティッグ・リンドベリのアシスタントとして、グスタフスベリ製陶所デザイン室勤務。1999-2013年武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科教授。1967年日本クラフト賞(日本クラフトデザイン協会)、1980年国井喜太郎産業工芸賞(日本工芸財団)、1986年「第1回国際陶磁器展美濃」グランプリなど受賞。
主なパブリックコレクション:ニューヨーク近代美術館、ヴィクトリア&アルバート美術館、東京国立近代美術館、茨城県陶芸美術館、武蔵野美術大学 美術館•図書館など。

