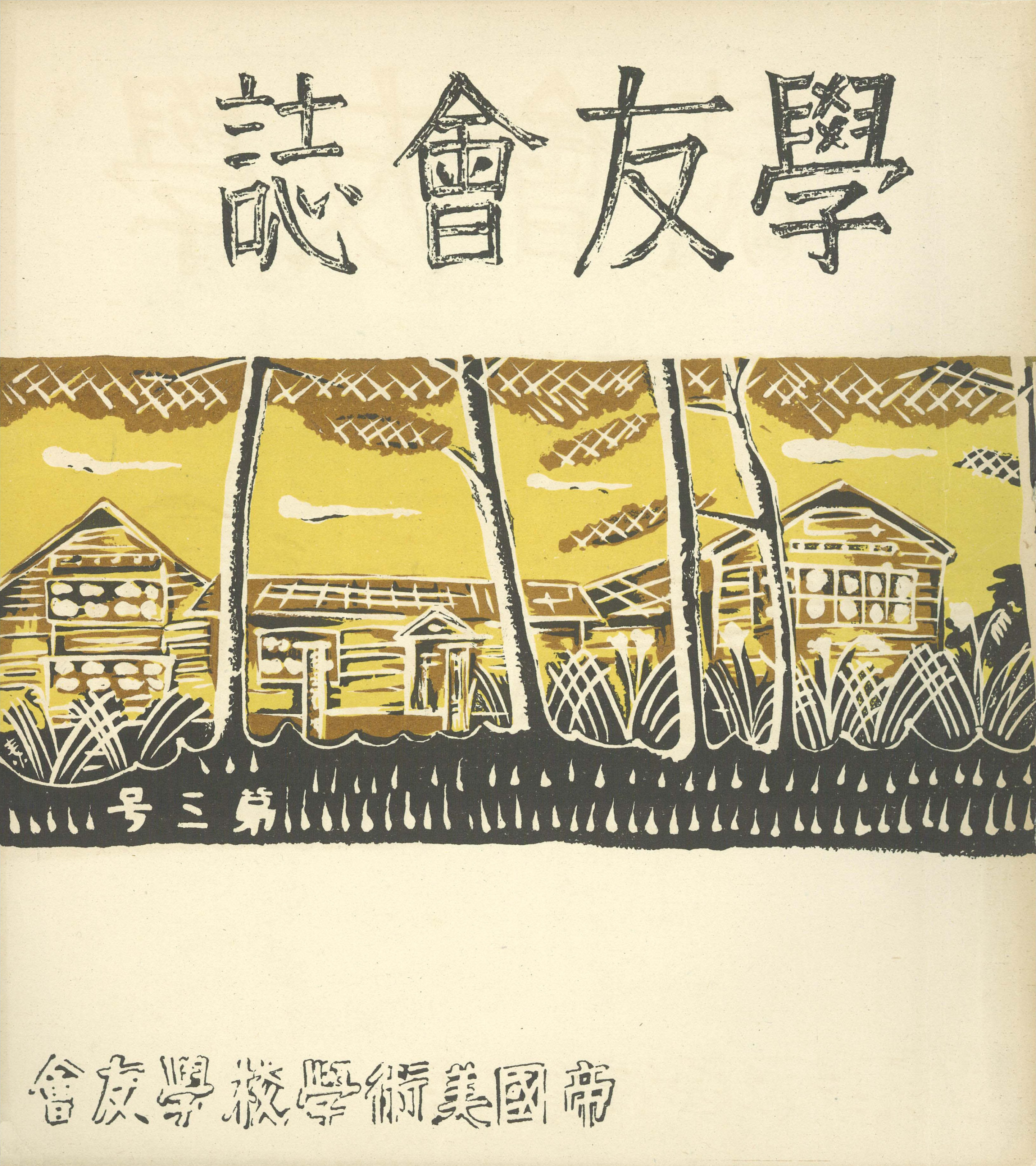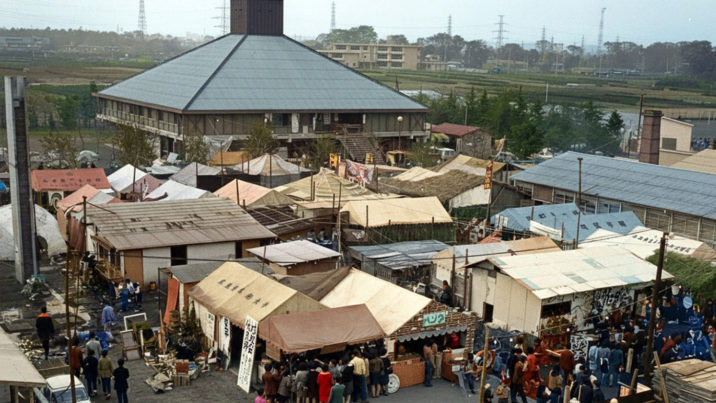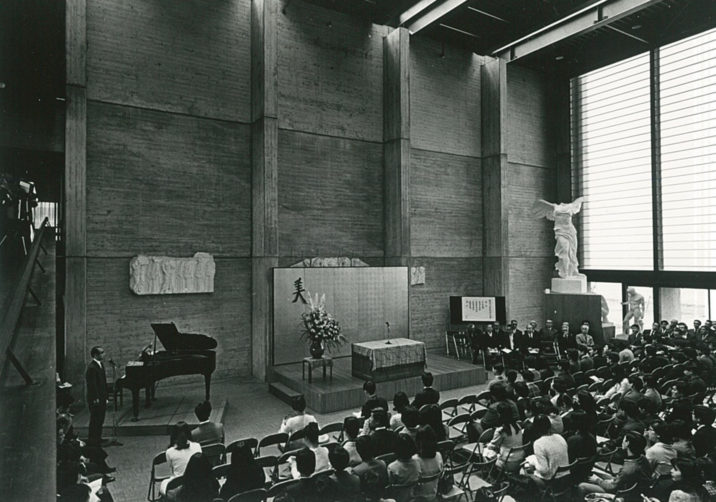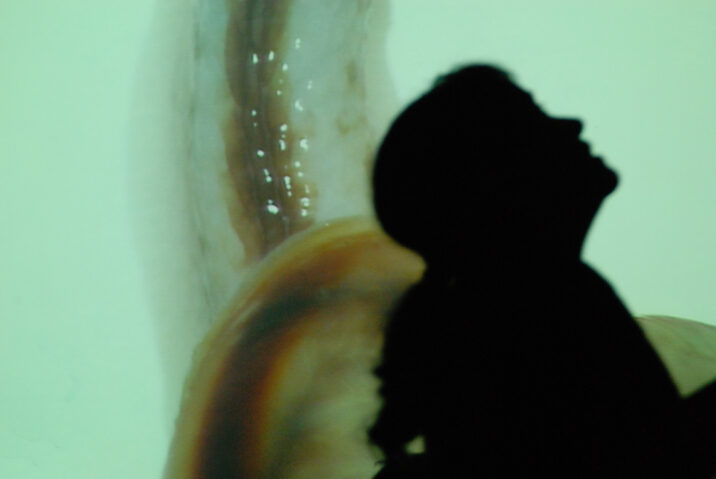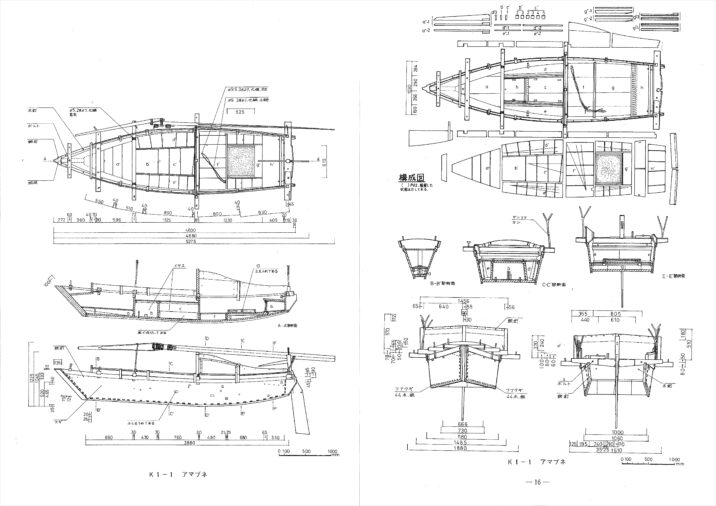たまたまのことには違いないが、「学友会誌」第3号にはふたつ、文豪・森鷗外に関係する文章が載っている。
まずは、この連載の初回で触れた宮永芳江の「渋江先生の思ひ出」。帝国美術学校草創期の教員だった渋江終吉の追悼文だが、終吉こそは、鷗外晩年の史伝三部作のひとつ『渋江抽斎』(19
もうひとつは、西洋画科の三年生だった神田美一の随筆「ロダンのお花さん」である。巨匠オーギュスト・ロダンのモデルになった「花
神田の文章を一読し、まずは20
太田ひさは愛知県に生まれ、明治時代半ばの19
ひさに会った神田美一は、岐阜県の出身である。
なぜ会いに行ったのか、むろん岐阜出身の縁によるのだろう。ひさが帰国し、岐阜にいることは、例えば「読売新聞」でも報じられていた(19
ただ、想像をたくましくすると、神田を動かしたのは、
19
突然の来訪にもかかわらず、ひさは「
持ち帰っていた彫刻2点が運び出され、ひさはそれに手を触れながら、
その一方で、ひさは「ほんとうに優しいお方で/こんなことも御座いました」
執筆当時、神田は東京の西郊、帝国美術学校に学んでいた。遠く岐阜へ思いをはせ、
言い添えると、短編「花
その後の神田は、帝国美術学校に籍を残したまま中国に遊学した。陸軍省嘱託として雲崗石仏の調査にあたったという。その傍ら、独立美術協会展にも出品したが、19
Series
「帝国美術」を読む
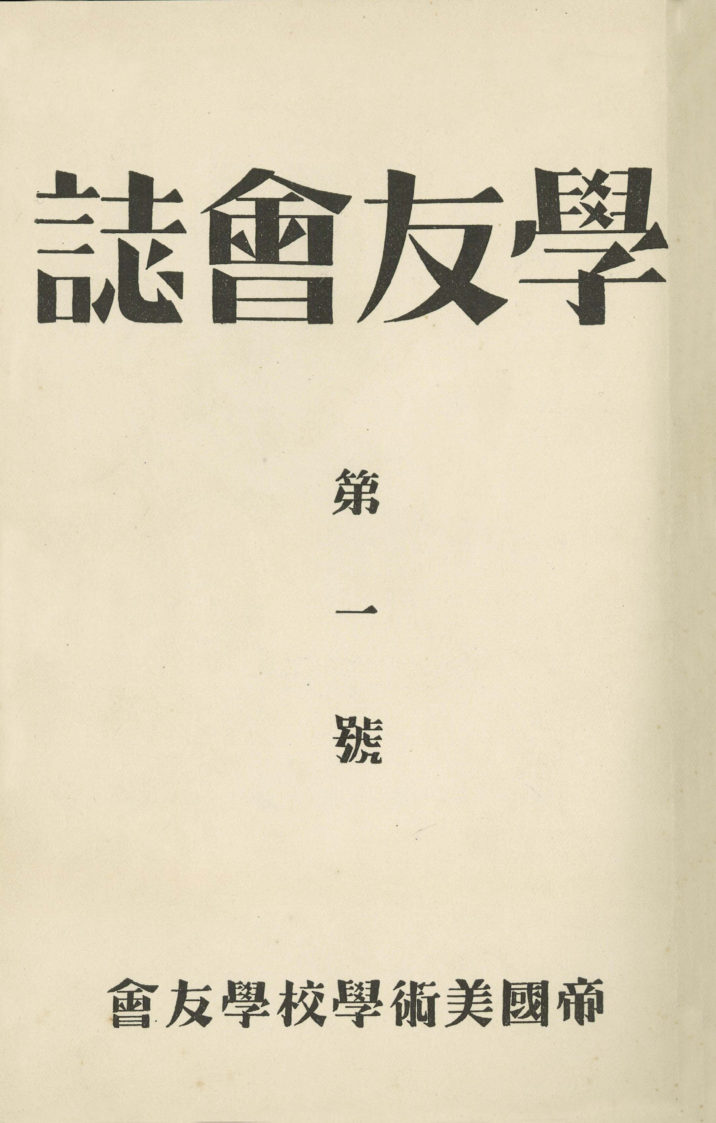
「帝国美術」を読む(1)宮永芳江「仮装行列記」
- キャンパスライフ
- #『学友会誌』
- #『帝国美術』
- #19
30年代 - #キャンパスライフ
- #仮装行列
- #前田恭二
- #創立記念祭
- #吉祥寺
- #宮永芳江
- #小田格一郎
- #工芸図案科
- #帝国美術学校
- #朱華染色刺繍研究会
- #東京美術学校
- #渋江終吉
- #西荻窪
コラム
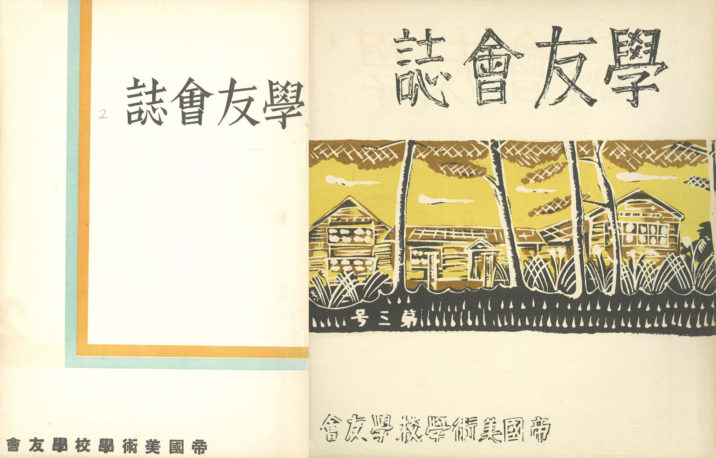
「帝国美術」を読む(2)磯部陽「私の蒐集郷土玩具に就て」(第2号)、「郷土玩具」(第3号)
加藤幸治(教養文化・学芸員課程教授)
- 課外のまなび
- #『学友会誌』
- #『帝国美術』
- #19
30年代 - #ナショナリズム
- #加藤幸治
- #同朋意識
- #大学コレクション
- #民俗資料室
- #福島県
- #美術館図書館
- #課外のまなび
- #農民美術
- #郷土玩具
コラム
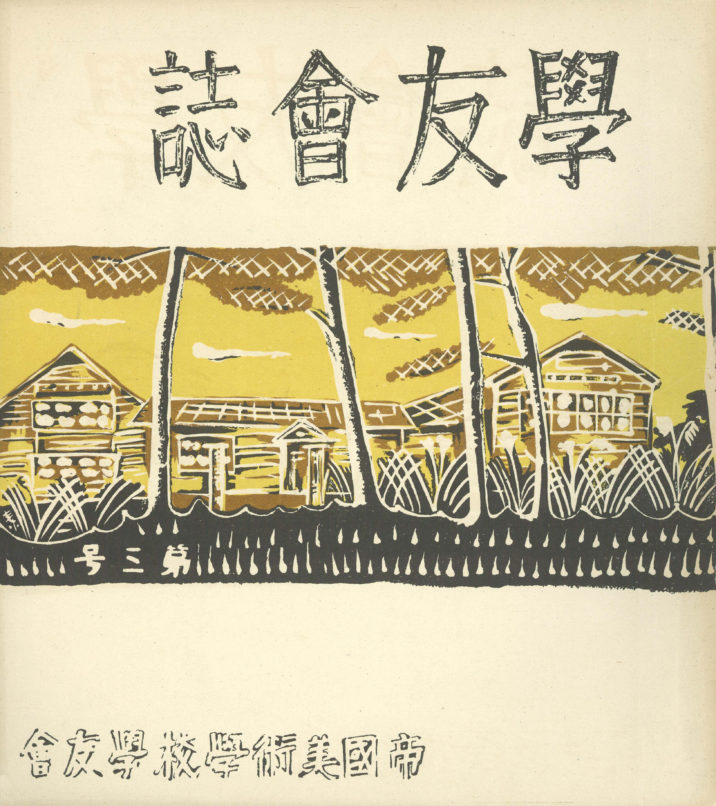
「帝国美術」を読む(3)神田美一「ロダンのお花さん」
- 批評
- #『学友会誌』
- #『帝国美術』
- #19
20年代 - #19
30年代 - #ロダン
- #前田恭二
- #太田ひさ
- #岐阜
- #帝国美術学校
- #彫刻
- #批評
- #森鷗外
- #渋江抽斎
- #渋江終吉
- #神田美一
- #花子
- #高村光太郎
コラム
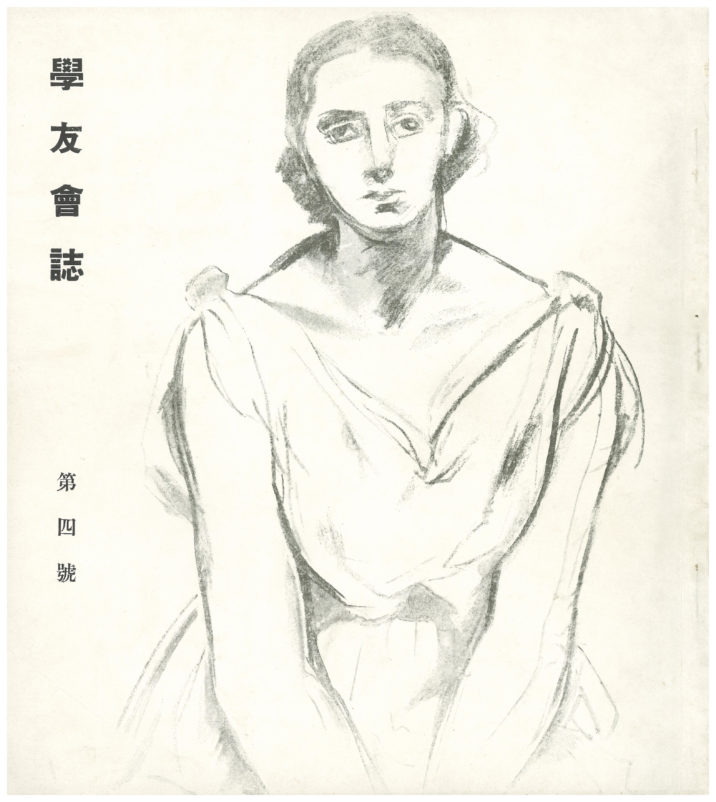
「帝国美術を読む」(4)田中富士雄「ベツトで溺死した男」
- 批評
- #『学友会誌』
- #『帝国美術』
- #19
20年代 - #19
30年代 - #JAN
- #コント
- #ジャン・コクトー
- #シュルレアリスム
- #ジュンヌ・オム
- #ハプニング
- #ハンス・アルプ
- #マックス・ジャコブ
- #前田恭二
- #創作
- #岡田三郎
- #川端康成
- #批評
- #掌の小説
- #斎藤茂吉
- #新感覚派
- #村山知義
- #柳沢孝子
- #水玉模様
- #浅原清隆
- #田中富士雄
- #短篇小説
- #自己消滅
- #草間彌生
- #荒木剛
- #菊地友一
- #青年美術家集団
コラム